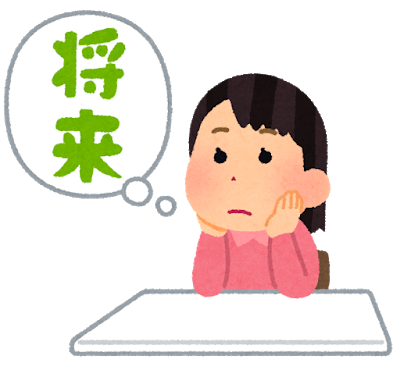「薬剤師の仕事はAIが発達するとなくなる」
「薬剤師はどんどん過剰になるから売り手市場は終わる」
このような話を聞いたことがありませんか?薬剤師は将来性がないというような話が時おり耳に入ってきますよね。こんな話を聞くと、とくに今から薬剤師を目指す方は不安に思ってしまうかもしれません。
今回は大勢の方が気になっている「薬剤師の将来性」ついてお話をします。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
薬剤師は売り手市場!求人数や薬剤師数から需要を見てみよう

2021年現在は、まだまだ薬剤師の売り手市場が継続中です。
しかし今後は、薬剤師の仕事が無くなるという意見も散見されています。本当に売り手市場が終焉を迎えるのかどうか、まずは求人数を見ながら考えていきましょう。
大手3社の求人数
- マイナビ薬剤師:60,637件
- 薬キャリ:25,088件
- ファーマキャリア:44,437件
※2021年5月時点
最初に「今、本当に薬剤師は売り手市場なのか?」を確かめておく必要があります。これは転職サイトやハローワークなど、各媒体で薬剤師求人が多いかどうかで確かめることが可能です。
2021年5月時点では、マイナビ薬剤師と薬キャリの2社だけでも「約8万件」の公開求人があります。単純に考えると「薬剤師8万人分の仕事がある」ということですね。
薬キャリに登録してみよう!
薬剤師の総数は「約30万人」なので、この2社だけで薬剤師全体の4分の1の仕事が確保されていると考えられるのです。
もちろん、各媒体で同じ求人が掲載されているケースもあるので、実際はもう少し低い見積りになります。
それでも、転職の際に「応募先がまったくない・・・」という経験をしたことがある薬剤師はほとんどいないのではないでしょうか。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
従事先別による薬剤師数
| 薬剤師数(人) | 構成割合(%) | |
|---|---|---|
| 総数 | 311,289 | 100 |
| 男 | 120,545 | 38.7 |
| 女 | 190,744 | 61.3 |
| 薬局の従事者 | 180,415 | 58.0 |
| 医療施設の従事者 | 59,956 | 19.3 |
| 介護保険施設の従事者 | 832 | 0.3 |
| 大学の従事者 | 5,263 | 1.7 |
| 医薬品関係企業の従事者 | 41,303 | 13.3 |
| 衛生行政機関又は保険衛生施設の従事者 | 6,661 | 2.1 |
| その他の者 | 16,856 | 5.4 |
引用元:平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
今後に薬剤師の仕事が無くなるかどうかを考える上で、薬剤師がどのような場所で需要があるのかもポイントになってきます。
「総数311,289人」に対して、薬剤師の従事先は「薬局・180,415人」・「医療施設・59,956人」・「医薬品関係企業・41,303人」がTOP3です。
具体的には「調剤薬局」・「ドラッグストア」・「病院」・「製薬会社」などが、薬剤師の主な従事先です。
もちろん、調剤薬局や病院など以外の場所で働く薬剤師も大勢います。
薬局や病院以外で働く薬剤師の職種や仕事内容・総まとめ!企業(製薬会社・医薬品卸など)・研究・開発・臨床・治験・DIなど…本当にたくさんの仕事があります。
働き方が多様化してきたことにより、副業や兼業スタイルで働く薬剤師も増えていますね。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
薬剤師の仕事が無くなるって本当?将来性はあるの?

薬剤師の今後の需要や展望はあくまで予想の話なので、「仕事が無くなると思う派」と「現状維持だと思う派」の両方の意見はどちらもあり得ます。
私は今後も薬剤師の売り手市場に変化はないと思っています。
薬学部の合格率は将来性にあまり関係ない
薬剤師の売り手市場が終わるという意見の中で、その理由として良く挙げられるのが「薬学部の合格率」です。
近年は、合格率が上がっていることからも、そのまま薬剤師輩出数が増加傾向を辿れば転職の競争率が高まり、薬剤師の売り手市場が終わってしまうという考えがあります。
しかし今の時点でも、薬剤師求人は溢れており、合格率の影響はほとんど受けていないことが証明されています。
2021年の薬学部合格率
- 国立大学の新卒合格率:90.79%
- 国立大学の既卒合格率:43.14%
- 私立大学の新卒合格率:85.10%
- 私立大学の既卒合格率:41.35%
「第106回薬剤師国家試験 大学別合格者数」では、国立大学と私立大学のいずれも合格率が高いです。
全体では「合格者数9,634名・合格率68.66%」と発表されていますが、この水準でもまだまだ多くの薬剤師求人が残っています。
年齢別の薬剤師数は?
| 総数(人) | 薬局 | 病院 | 診療所 | 介護保険施設 | 大学 | 医薬品関係企業 | 衛生行政機関又は保健衛生施設 | その他の者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 311,289 | 180,415 | 54,150 | 5,806 | 832 | 5,263 | 41,303 | 6,661 | 16,856 |
| 29歳以下 | 38,783 | 20,330 | 12,397 | 101 | 3 | 491 | 3,773 | 926 | 852 |
| 30~39歳 | 79,076 | 44,899 | 16,869 | 476 | 46 | 11,180 | 9,572 | 2,432 | 3,611 |
| 40~49歳 | 72,763 | 44,165 | 11,567 | 898 | 159 | 1,409 | 9,906 | 1,477 | 3,132 |
| 50~59歳 | 62,369 | 36,073 | 8,179 | 1,634 | 186 | 1,269 | 10,682 | 1,426 | 2,920 |
| 60~69歳 | 41,437 | 25,352 | 4,305 | 1,855 | 277 | 854 | 5,058 | 373 | 3,361 |
| 70歳以上 | 16,771 | 9,596 | 842 | 842 | 161 | 60 | 2,312 | 27 | 2,930 |
引用元:平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
毎年、約10,000人ほどの薬剤師が誕生しても、それと同じ程度の薬剤師が引退していくと考えると、やはり合格率の高まりによって薬剤師の売り手市場が終わることは無さそうです。
根本的に合格率と合わせて受験者数もポイントであり、短期間で若年層の薬剤師が急激に増えるためには受験者数が今以上に増えなければなりません。
2021年に実施された国家試験の受験者数は14,031人です。
受験者数まで掘り下げていくと「高額な学費」や「6年制という長い期間」など、経済的な理由が改善されなければ大幅に受験者数が伸びることも無さそうな雰囲気があります。
「薬剤師は10年以内に飽和する」はもはやネタ
薬剤師の数はたしかに毎年増えていっています。それは下のグラフを見ても明らかです。

参考:平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況
薬局や医療施設に従事している薬剤師の数をグラフ化したものですが、どちらも右肩上がりになっていますね。ただし増えているのは薬剤師数だけではありません。
調剤薬局の数もドラッグストアの店舗数も毎年増え続けています。
むしろ店舗数の増加に薬剤師数が追いついていない状況で、現場ではより薬剤師不足が深刻になっているのが現状です。
事実、「うちの店舗は薬剤師がたくさんいるから余裕だ」なんて言っている薬剤師はおらず、「薬剤師がたりない」「新店舗ができて薬剤師がどんどん減らされてツライ」といった声をよく聞きます。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
ただし薬剤師の有効求人倍率は年々下がってきている
有効求人倍率とは、求職者1人に対してどれくらいの求人があるかを示したものです。
たとえば有効求人倍率が10なら、求職者1人に対して10の求人があることになります。
実はこの有効求人倍率は、年々下がってきている、つまり1人あたりの求人が減ってきているのが現実です。
| 年度 | 有効求人倍率 |
|---|---|
| 2016年3月 | 6.60 |
| 2017年3月 | 6.09 |
| 2018年3月 | 5.35 |
| 2019年3月 | 4.55 |
| 2020年1月 | 3.61 |
参考:一般職業紹介状況
ご覧のように、2016年には6.60倍だった有効求人倍率が、2020年には3.61倍にまで下がっています。1人あたりの求人数がおよそ半分にまで減っているのです。
しかし薬剤師が過剰になる心配はまだありません。「人手がたりなくて困っている」という薬剤師の声はよく聞くものの、「薬剤師が多すぎていらない」という声は一度も聞いたことがないからです。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
薬剤師の業務効率化でも需要は変わらない

- 勤怠管理システム
- 給与計算ソフト
- AI(ロボット)
- 面接支援システム
- 人事管理システム
最近は、ITの進化によって業務を効率化できるシステムがたくさん登場していますね。
たとえば、タイムカード制から勤怠管理システムに移行すると、スマホやパソコンで従業員の勤怠管理を簡単に把握できるようになります。
これによって今までタイムカード作成や管理に費やしていた時間を大幅に短縮することが可能です。
業務効率化の延長には「人件費の削減」という大きなメリットがあります。
このメリットを簡単に説明すると、今まで2人で仕事をしていたところを業務効率化によって1人で出来るようになると、新たに人材を確保する必要がなくなるわけです。
薬剤師の主な業務効率化システム
- 保険薬局用電子薬歴システム
- 対話型電子薬歴管理システム
- 保険薬局用コンピューター
- 薬局情報共有システム
- ヘルスケア手帳サービス
「PCH」の製品だけでも、薬剤師の業務効率化が可能なシステムはたくさんあります。
しかし薬剤師の業務は薬機法で「対面指導」というルールが設けられているので、業務を効率化しても薬剤師数をゼロにすることはできません。
また業務効率化による人件費の削減は、仕事量との関係も非常に深いため、そもそも患者さんが少ないお店ではこうしたシステムを導入するメリットがほとんどない場合もあります。
処方箋の電子化はどうなのか?
- 医療機関の間で情報共有をしやすくなる
- 処方箋の偽造や再利用の防止ができる
- 処方箋の印刷コストを削減できる
- 処方箋の保管が楽になる
- 処方情報の入力等の作業を軽減できる
2018年4月から、処方箋の電子化がスタートしました。
これによって、主に「医療機関の間で情報共有がスムーズになる」というメリットがあります。日本の医療システムを向上させるための大きな一歩といった改革です。
またお薬手帳は、マイナンバーに導入することが検討されており、今後の医療システムは着実にIT化が進んでいくと思われます。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
オンライン診療はどうなのか?
薬剤師の業務は「医師が処方箋を発行」→「薬剤師が処方箋を元に調剤」というプロセスがあるため、薬剤師の業務改革を行うためには日本の医療システムとして考えていくことが必要不可欠です。
日本の医療システムは「離島における人手不足の課題」などから、在宅医療や地域医療をどのように改善すべきかをよく議論されています。
さまざまな構想がある中でも、今後注目しておきたい1つに「オンライン診療」があります。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
AIが導入されたらどうなのか?
AIが導入されると薬剤師の仕事は真っ先になくなるとはよく言われる言葉。AIに調剤をやらせた方が過誤も出ないしスピードも上がると言われています。
しかし薬剤師の仕事は何も調剤だけじゃないですよね。患者さんの服薬コンプライアンスを上げるために服用タイミングを変えたり、患者さんの不安を少しでも取り除けるような服薬指導だって必要です。これがAIにできるでしょうか?
それに冒頭でも言ったように薬剤師は対面指導がルールなので、完全にAIに仕事を奪われるとは考えにくいです。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
テクニシャン制度が導入されたらどうなのか?
テクニシャン制度とは、薬剤師の助手のような存在の方のことです。薬剤師の代わりにピッキングをしてくれるので、薬剤師はそれ以外の監査や患者さんとの対応をすることになります。
テクニシャン制度はすでに欧米で導入されている制度で、日本でも導入しようという声が挙がっていますね。しかしテクニシャン制度がもしも導入されたとしても、調剤以外の仕事は薬剤師がしなければなりません。
テクニシャン制度によって薬剤師の仕事がなくなるとは考えにくいです。
最近では医療事務員でも薬剤師の監視の元でピッキングができるようになりましたが、だからと言って薬剤師の仕事が奪われたとか減ったとかいう話は聞かないですよね。
【厚労省通知】薬剤師以外(調剤事務など)、のピッキング・一包化の実施が可能に!薬剤師法に照らし、「調剤行為」の範囲を再定義してみた。
10年後も生き残れる薬剤師になるにはどうしたらいいか?

「薬剤師数が増えても薬局やドラッグストアの店舗が増えているから薬剤師は過剰にならない」
「AIやテクニシャン制度が導入されても、薬剤師にしかできない仕事はまだまだある」
これらはたしかに事実です。しかしだからと言って「薬剤師の将来性はまだまだある!」とあぐらをかいていては、10年後にも生き残れる薬剤師にはなれません。
勉強や経験を怠らない
処方せん通りに調剤して、差し支えのない服薬指導をするのは誰でもできます。生き残れる薬剤師になるためには、さらに知識や経験を増やしていくことが大切です。
たとえば専門薬剤師や認定薬剤師が代表的ですね。スペシャリストになるべく1つの分野を極めるもよし、ジェネラリストになるべくさまざまな分野で資格を取るのもよし。
薬剤師の資格は一度取ってしまえば更新がないので、永久的に使えます。しかし免許を取得した後にどれだけ勉強しているかで薬剤師の質は大きく変わるものです。
 薬局薬剤師
薬局薬剤師
人気の薬キャリ薬キャリの口コミ・評判やメリット!薬剤師転職サイトの中でも秀逸で薬剤師の半数が登録
在宅医療もできる薬剤師になる
日本は間違いなくこれからも高齢者の割合が増えていきます。総務省が発表している以下のグラフを見ると高齢者が顕著に増加していることがわかるでしょう。
すでに4人に1人が65歳以上の高齢者である今、間違いなく高齢者に向けた医療サービスの需要が高まっていきます。そうなることで今よりももっと在宅医療の必要性が高まると考えられています。
とはいえいきなり在宅医療をさせられて何をしていいかわからないと困る薬剤師が多いのも事実。
在宅医療に対応できるように以下のスキルを身につけておくとよいでしょう。
- 患者さんが本音で話してくれるようなコミュニケーション能力
- 患者さんの生活スタイルを考慮したお薬の提案
- 患者さんが自分でできることを見極める
在宅医療では患者さんの家にあがってお話をします。場合によっては患者さんと二人きりでテーブルを囲ってお茶をすることもあるものです。
他所様の家にあがって話をするというのは思っているよりも緊張するものです。ここで緊張しすぎずに患者さんとコミュニケーションを取れるスキルは必ず必要となります。
また在宅医療を実際に始めるとわかるのですが、多くの患者さんは薬の飲み残しがあります。なぜ飲み残してしまうのかを患者さんとの会話の中で掴み、生活スタイルに合わせた飲み方や処方変更を提案できるスキルも必要です。
在宅に行くと何でもかんでも薬剤師が「患者さんのために」とやりがちですが、患者さんができることは患者さんにやってもらい、お手伝いが必要なことだけ手を差し伸べる見極めも必要となります。
【2025年問題】高齢化が進む日本で薬剤師がはたすべき役割は?在宅医療・併設複合型の店舗増加・「健康の起点」となることがカギか
英語や中国語を学ぶ
実は観光客の多い地域では、英語や中国語を話せる薬剤師はとても重宝されます。英語ができる薬剤師は探せばまだいるものの、中国語となると滅多にいません。
そのため海外の患者さんに満足のいく接客ができないと悩まれている方は多いものです。とくに観光客の多いドラッグストアでは日本人よりも海外の方へ対応することが多いくらい日常で英語や中国語が必要とされています。
「薬剤師×英語」、「薬剤師×中国語」とスキルを結びつけることで貴重な存在になることが可能です。
調剤薬局や医療施設に関連する改革は注目しておきたい!

従事先別による薬剤師数から見ると、「調剤薬局」や「病院」などに関連する改革に注目しておけば、今後、薬剤師の売り手市場の変化もいち早く抑えられそうです。
とくに薬剤師総数の半分以上が調剤薬局で働いているため、ここの従事者数が大きく減るような改革がやってきた時こそ薬剤師の売り手市場が終焉を迎える時かもしれませんね。
とはいえ、まだまだ薬剤師の需要が急激になくなるということは考えにくいです。冒頭でもお話をした通り、マイナビ薬剤師や薬キャリだけでも合わせて10万件以上の求人があります。
コンサルタントと直接会って面談ができるマイナビ薬剤師はとくに登録しておいて損のないサイトです。